バイデン政権は28日、議会に対して総額330億ドル/約4.3兆円ものウクライナ支援パッケージを要求して注目を集めている。
参考:Putting Biden’s new whopping $33B Ukraine package into context
参考:White House’s $33B Ukraine aid bid already tangled up in Congress
今回の戦争で防衛産業企業が儲かるという構図は必要悪としか言いようがない
バイデン政権が議会に要求した歴史的支援パッケージに関する詳細は不明だが、総額330億ドルの内204億ドルが「ウクライナに対する追加の安全保障と軍事支援」「NATO加盟国や他のパートナー国と協力して欧州の安全保障を強化するための取り組み」「ウクライナに提供した米軍装備の埋戻し」などに使用されると報じられているので、330億ドルもしくは204億ドル全てがウクライナに引き渡す武器に化けるという意味ではない。

出典:DoD News photo by EJ Hersom
ただ3回に分けて発表された累計34億ドルの支援パッケージと204億ドルの軍事支援を合わせると、米国がアフガニスタン向けに拠出した年間援助額の2倍以上、イスラエル向けに拠出している年間援助額の7倍に相当、先月した成立した140億ドルと今回の330億ドルを合わせると国防総省の年間予算(国防予算ではなく国防総省の予算)に匹敵すると報じられいるのが興味深いが、歴史的支援パッケージで最大の恩恵を享受するのは米防衛産業企業や米国に製造拠点がある海外の防衛産業企業だろう。
すでにウクライナ向けの支援パッケージに含まれる武器を供給する米企業の株価は急騰、国防総省からの受注額が最も多い上位5社は第1四半期だけで1,600万ドル以上のロビー活動を費やし、ウクライナ向けの武器供給に食い込むため政府や国防総省関係者と議論を行っているらしい。

出典:U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua Leonard
勿論、国防総省から直接仕事を受注できる元請け企業(ロッキード・マーティン、ボーイング、レイセオン、ノースロップ・グラマン、GE、BAE、L3Harrisなど)の下には米国に製造拠点がある欧州やアジアの防衛産業企業(フィンカンティエリ、ラインメタル、タレス、STエンジニアリング、ハンファディフェンスなど)がぶら下がっており、様々な思惑が絡んだ激しい売り込み活動が水面下で行われているはずだ。
この手の話に嫌気がさす方もいるかもしれないが、ウクライナが必要とする武器を供給すると米軍の在庫にギャップが生じるので、これを埋め戻さなければ世界全体の軍事バランスに影響がでるため今回の戦争で防衛産業企業が儲かるという構図は必要悪としか言いようがない。
欲を言えばここに日本の防衛産業企業が割り込めれば良いのだが、国防総省の仕事を直接受注するために米国人を雇用した製造拠点を米国内に保有していなければならない=国防総省の受注を自国に持ち帰って製造して納めるというのは基本的にNGなので、元請け企業と提携して仕事を回してもらうが最も現実的と言える。

出典:Public Domain M109A7の開発・製造は現在BAEが請け負っている
しかし米国市場への進出を狙う海外企業も現地拠点の設立と米国人雇用を積極的に行っているので、中々日本企業がパッと行って受注を獲得してくるのは難しいだろう。
関連記事:海外進出のススメ、世界中の防衛産業企業が進出する年間予算80兆円台の米国市場
※アイキャッチ画像の出典:U.S. Air Force photo by Mauricio Campino
| お知らせ:記事化に追いつかない話題のTwitter(@grandfleet_info)発信を再開しました。 |





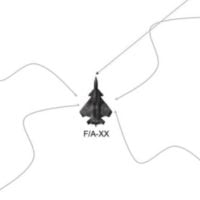










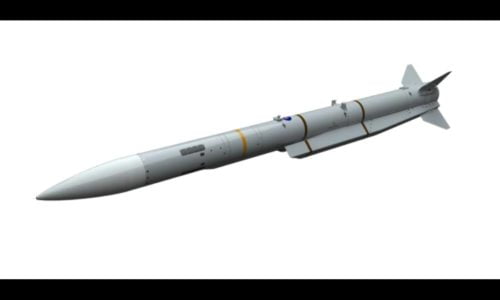




レンドリース法復活確定の直後にもう(笑)
ロシアの侵略意図を完全に潰す気満々じゃないですか。
まぁ、核脅迫しながら侵略戦争始める手合なんて、
短期的に欺いてボタン押させないように誘導する相手ではあるかもしれませんが
長期的な外交関係を結べる相手ではありませんし。
波及効果と予想される更なる追加措置と併せて、コロナ禍を吹き飛ばす特需と化すかもしれませんねこれ。
そこで問題になるのはロジスティクスの混乱でしょぅ。酷かったときよりかはマシとはいえ、相変わらずコンテナ不足や船舶不足、コロナ対策により荷卸しの効率悪化等の問題が起きてる以上、よその国から材料・部品を買おうにも時間とコストがえらくがかかってます。コロナ以前の国際分業化体制へ最適化された産業を緩和させるのはもう少し時間がかかるのではないでしょうか。
あとは、細かな部品類はほっとんど中国製ですから、少し前に中国製部品の除外の取り組みというのもやってましたが、そうは言ってもでしょう。あくまでも中国の立場はウクライナ・ロシア間の戦争への不干渉なので、それを理由に部品の輸出を制限するかもしれません。これは日本だけでなく記事に出ている防衛産業全般の問題ですから、どうなるかは様子見でしょう。
供給網混乱の代名詞、半導体は組込みCPUなんかだと未だにインダストリーグレード(耐環境性能の良い割高なやつで自動車や特殊用途)はおろか民生グレード(汎用品)も全く手に入らない。
平時でもインダストリーグレード以上に供給がタイトな軍用グレード(耐環境性能最強)は最早生産してるのかも怪しいレベル。
ビジネスとして小粒な軍用グレードの優先順位は政治のバックアップでも無い限り後回しにされそうな…
軍用は骨董品みたいなプロセスを使ってるのでそれなりにキャパシティーはあるのではないでしょうか(ほかに客がいない)。
軍用グレードといっても温度範囲が広い選別品やパッケージの違いだったりですし。
第一弾でこれって、規模的にはロシア自体を潰す気が出まくりな気がする
核脅迫して、いつ使ってもおかしくないって断定されてる国は人類初だし
これを見逃したら民主主義は終わりそうな上、人類の生存すらいつ終わるか怯える羽目なるし
ロシアの味方してる国以外は許容出来ないでしょうね
核大国のアメリカ政府自身が恐怖を一番感じてるのかもです
防衛産業に流れたドルはどこかに消えるわけではなく、最終的には従業員の給料になってアメリカ経済を回すわけですから、軍事支出が多いことは決して悪いことではありませんよね
軍事費が少なければ少ないほど良いと考える人が何故か日本にはたくさんいますが
防衛産業に流れたルーブルはソビエト経済を回してくれましたか…?
ハコモノに流れた税金は地方経済を回してくれましたか…?
トリクルダウンなる言葉が大いに騒がれた時期もありましたが、一部が潤えば全体も潤うというのは、実際の経済ではなかなか難しいのです
そもそもソ連の経済の基本は、石油などの資源を西側国家に売って成り立っていました
自力で経済を回して居なかったので、その前提自体が成り立たない
なるほど、自給自足に近いNorthKoreaの様な国ならトリクルダウンが成り立つ訳だ
反対に円安や資源価格の値上がりで右往左往している日本ではトリクルダウンは成り立たないということになる
その論ならば戦前の日本や旧ソ連などは軍事費をいくら増やそうが経済的困難とは無縁だったはずだけど
「軍事費が少なければ少ないほど良い訳ではない」を勝手に「軍事費は多ければ多いほど良い」に脳内変換してない?
軍事費が「全て」経済に回る、とは誰も言ってないし、「身の丈」の問題も当然あるよ。
> 軍事費が「全て」経済に回る、とは誰も言ってないし
「防衛産業に流れたドルはどこかに消えるわけではなく、最終的には従業員の給料になってアメリカ経済を回す」と言っているから「全て」経済に回ると言っていると理解したけど?
> 「身の丈」
「軍事支出が多いことは決して悪いことではありませんよね」
身の丈に合った支出なら「多い」と表現する必要はないよね
旧ソ連が経済的困難に陥ったのは、トリクルダウンのまったく起きない中間搾取構造の体制だったので自業自得でしょう。
戦前の日本は、造船関係者は末端の工員まで大いに潤っていましたよ。
ただ、国民全体に行き渡るには、そもそも国の経済の規模が小さすぎたというだけの話です。
アメリカでは昔も今も、特需となった業界は作業員を雇うために大盤振る舞いしますから(特需が終わればスッキリと解雇しますが、お互いに割り切った関係なので問題ない)アメリカ国民は大いに潤うでしょうね。
中間搾取されたルーブルはどこかに消えるわけではなく、最終的には党員の資金になってソビエト経済を回すわけですから、中間搾取が多いことは決して悪いことではありませんよね
中間搾取が少なければ少ないほど良いと考える人が何故か資本主義国家にはたくさんいますが
ソ連経済が回っていたことはないから
だから破綻したの
そりゃ回らないさ
投資が軍事産業に集中すれば民生部門は先細りになる一方
> 旧ソ連が経済的困難に陥ったのは、トリクルダウンのまったく起きない中間搾取構造の体制だったので自業自得でしょう。
?
トリクルダウンというのは一部の富裕層も稼いだ金は使うもの、それが富裕層以外の国民に廻り回って国民全体が潤うという考え
その考えに立つなら中間搾取層も結局は金を使うはずで、中間搾取層がいるからトリクルダウンが起きないというのはそもそものトリクルダウンの前提に矛盾している
そもそも軍需産業が、そんなに儲かるものではないし、経済全体からみたら微々たるものですからね。
軍需産業が経済を支配しているなんて妄想ですから。
国民総動員なんてかかる場合は、既に国家の危機ですから経済も滅茶苦茶になってますしね。
ここの管理人が言ってるのもサプライチェーンの維持のために規模の経済を求めるべきって話で
別に武器輸出で儲けろという話ではないからね
兵器自体はあんまり再生産性のある産業じゃないし顧客も市場も限られている
大体世界中で兵器が大量消費されるような状態になったらその時点でサプライチェーンが崩壊してるで
GDPが増えることが社会厚生の改善につながるわけではないというのが一つ。
適切な再分配を行う仕組みがなかったというのがもう一つ。
軍事は穴掘って埋める程度には公共事業としての効果がある
戦前の日本は軍事よりは社会インフラに投資した方が厚生の改善につながった。
現代のアメリカは既に社会インフラが十分に整っている
戦前の日本は超格差社会で国民の半分が農民で企業も育っておらず雇用規制もほとんどなかった
ことはそんなに単純じゃなくて、アメリカは高付加価値製品の工場しか残っていないという問題があります。半導体しかし製薬しかり、今回の兵器についても最終的な組み立てくらいしかアメリカに工場がなく、そんなに従業員が多いわけではないです。そして部品・素材はほかの国の企業に発注する必要があり、また利益も役員報酬や配当金に吸い取られて、結局一般市民に供給されるドルは言うほど大くないはずです。
この辺りは日本も、増えた防衛費がオスプレイとF35に吸い取られていて、あるいはコマツが撤退したというニュースと合わせてもめてましたので、あまり経済対策的な観点でメリットを語るのはイマイチだと思います。
この手の話に嫌気がさす方もいるかもしれないが
まずはここから改善をしていく必要がありますね。このブログでもこういった前置きが必要なのがとても悲しいですね。
防衛は武器を持つことだけではなく、研究開発、生産ライン、整備施設、これらが機能して初めて防衛となりますからね。
壊滅的な国内の軍需産業ではとてもとても継戦、抗堪性があるとは言えません。スタートアップ企業の支援、攻撃的防衛装備輸出の法改正、この2点を推進してほしいものです。
身も蓋もない言い方になりますが、こういった議論を大っぴらに出来る政治家や環境は、現在の票田である高齢者の方々が他界されないと出来ないでしょうね。
20,30年後ですか?個人的には半分諦めていますが、間に合うといいですね。
年齢だけで一纏めに分類するのはどうでしょう?
若ければ防衛力強化に積極的ということは無くて、日本の選択肢をきちんと説明してこなかった政治·いわゆる有識者·メディア等が複合的に創り出した現状です。
反戦デモに嬉々として参加している様なジジババは、同世代の人達から見ても異質だと思いますよ。
ちょっと古いデータですが、平成30年の自衛隊・防衛問題に関する世論調査はご覧になりましたか?
戦争に巻き込まれる可能性があると答えたのは30以下が48.9%、60,70以上がそれぞれ33%、29.2%です。
自衛隊に期待する役割についても、災害派遣(50代)、島嶼防衛(40代)、弾道ミサイル対応(30歳以下)と年齢が下がるに連れ強度が高くなっていきます。
統計上、若年層の方が危機意識が強く、現実的かつ具体的な防衛手段を意識しています。
さらに、防衛意識のみならず、政治においても同様です。各世代ごとの政党支持率はご覧になりましたか?どの調査においても、反戦、反自衛隊、反防衛費増額を目指す種々野党の支持は高齢世代が母体です。
客観的なデータを読みますと、残念ながら世代間での防衛問題に関する大きな意識差が浮き彫りになってしまうんです。
そして、主観的にも私も最近頭が固くなってきなあって自覚する年齢です。上の世代の方々はもっとそうでしょう。だから、半分諦めているんです、結局私達も投票しても絶対数が足りず、ただ環境が変わる事を待つだけで、下の世代に押し付けることになりそうだな、と言うことに。
まあ世論調査が正ならば、ロシアの蛮行をロシア国民が支持しているのも正ですよね?
世論調査なるものが、対象の選択·調査の方法·調査主体の意思の混入等々によって、いかようにも偏移するのは常識と思いますよ。
若い世代の危機意識って、実感としてありますかね?
だったら、もっと選挙に行くんじゃありませんか?
危機意識はあるけど、選挙権は行使しない不思議な世代ですか?
なるほど、世論調査は信頼できないデータであるとおっしゃるわけですね。それは確かに一理あります。
では、hiroさんにて
若ければ防衛力強化に積極的ということは無くて
という客観的かつ検証可能な信頼できるデータをご提示ください。お話の続きはそれからにしましょう。
ここに至ればやむを得ないとはいえ、アゾフ連隊等はCIAの息がかかっているだろうし、バイデンの利権があるのも言われている。
バイデンの中途半端なやり方も気になる。
物価上昇による支持率低下を誤魔化す為にも、良いネタ過ぎるよな。
なるほど米国に拠点が無いと売り込むのは難しいというのは、極めて真っ当な話なので日本企業の参入が難しいのは当然ですか。
とはいえ昨今の物流混乱で、ある程度自国で賄える工業基盤を維持できている国というのは、そんなに多くなくて、西側で比較的出力が出せるのは韓国と日本ぐらい。現状で及び腰の韓国は、この話にどれくらい乗っかるのかがわからないので、日本もチャンスと言えばチャンスなんでしょうけどね。
とりあえず2次下請け程度の部品レベルから乗っかるのが良いのではなないでしょうか。
素材関係の企業が入っているのでは。
大きな声で言えないだけで。
部品や素材は普通に乗っかってるでしょ。
まいど不思議だなあ、と思うのは「米国の軍産複合体がー」と、なんなら「武器屋のために(米国が)火を点けてる」くらいの極論を言う人は一定数いるわけです。
それならば、同じ理屈は他の国だって当てはまるだろ、と思う訳ですが、そういう指摘をする人をほとんど見かけたことはないです。
「中国の武器屋がー」とか「ロシアの武器屋がー」とか聞いた試しがない。
実際のところ、スイスとかドイツ、フランスや北欧の国々の武器屋も、けっこう政治家の汚職も絡んでえげつない商売してると思うんですが、戦争経済による利益という文脈で引き合いに出されることは稀です。
なぜか、いつも米国(もしくはイスラエル)の軍事産業ばかりが批判の対象にされますよね。
単に、不勉強で武器屋と言えば米国のそれしか知らないのか、それとも世間のミスリードを誘うためにわざと言っているのか。
まあ、イメージ的に前者の可能性も高いですけどね。
「アメリカはめちゃくちゃ世界中に武器を売りまくって稼いでいるんだろ!」と言う人に、「いやいや議会を通さなきゃ勝手には売れないから」と言うと逆に驚かれたり。偏見ですよね。
永世中立を無防備平和主義とカンチガイ美化して思っている人にスイスやスウェーデンは「武器輸出国で有名ですよ」と言うとこれまた驚かれたり。
その手の方々って様々な方面から情報を精査したり筋道立てて考えてみたりする習慣に乏しく、「それっぽく説明出来そうな筋書き」に飛び付いてるだけですよね。したがって、陰謀論とは極めて相性がいい。
今回の件でアメリカの一部軍事企業には仕事が大量に降ってきて嬉しい悲鳴でしょうが、アメリカ全体ではインフレが加速し経済が傷んでいる。
政治家にロビーやら献金をしているのは軍事企業ばかりでなく、大口献金者にはウクライナ戦争で大損失を出している向きも多いでしょう。
とまぁ、アメリカの景気動向を考えてみるだけでも軍産複合体が云々というのは胡散臭いと分かりそうなものですが、「◯◯社製兵器を◯億ドル分供与」などというニュースばかり流されると、そういう人らが出て来ても仕方ないのかも知れませんねぇ…
たかだか4兆円程度で第二の仮想敵国ロシアをボロボロに出来るなら安いもんだね。
アメリカ人は死なず、ウクライナ人が代わりに死ぬ気で戦ってくれる。
結束が揺らいで存在意義が失われていたNATOも米国を盟主として反ロシアで一致団結。
ロシア側のプロパガンダに全てアメリカの思い通り、ってのがあるけどこれに関しては(現時点では)間違ってない。
これまでのシナリオは、ウクライナが予想外に大奮戦するという状況も含めて、全てアメリカの利益になっている。
ロシアをボロボロにすると戦後中国に頼るしかなくなり、中国のお金があればロシア軍はある程度回復できるかもしれません。そしてロシアは中国に頭が上がらなくなるという展開が怖いですね。まぁそうなると中国は欧州の敵になってしまいますが。
かといってロシアがウクライナに勝つと害がありすぎるので、今はウクライナを勝たせることが大事でしょう。
中国の支援でお金があっても、半導体や工作機械の制裁が続く限り、ロシアの軍備再興はかなり厳しいと思われます。
特に戦闘機や戦車のエンジンを作る工作機械は、日本とドイツの独壇場なので、制裁を食らい続けると最低限の装備すら調達できない可能性があります。
素材は中国経由でなんとかなっても工作機械は確かに難しいですね。中国の工作機械も日本や欧米製だし。使い道はチェックされるでしょう。
冷戦時代に東芝機械のCOCOM違犯が大問題になりましたが、工作機械は最強の戦略物資かもしれないな。
ロシアが中国の手下になったら今度はインドもロシアを切らざるを得ない
マトモに戦う支援相手の国に会えてアメリカさんも嬉しいのかも。
汚職の種にする国や後でテロしに来るようなのばかり相手にしてきた後だし。
見方によるけどアメリカ(と言うかバイデン一味?)はやり手だね。自分達の手を汚すことなくウクライナを全面に出してロシアと戦争。軍需産業は儲かるわ、ロシアは弱体化するわ、欧州はアメリカ依存深めるわで一石二鳥どころか、三鳥も四鳥も。
まあ挑発に乗るロシアがアホと言えばそれまでですが、よく見ると30年前の湾岸戦争と似たような構図だったりする。あの時もイラクは悪者にされてめちゃくちゃにやられた。フセインもだが独裁者は戦争に誘導しやすいんだろうな。
結果論で言えばそうでしょうが、開戦前の下馬評通りウクライナ政府・軍が数日で崩壊していれば、欧州や台湾の2正面で直接対決しなければならなくなるアメリカに、挑発の意図があったとすればそれはやり手というより無謀というものでしょう。
現状においても2月24日以前より欧州で核戦争のリスクが格段に増した状況は、アメリカとしてもかなり緊張感をもっているでしょうね。
もしそうなったら対中シフトどころではなくなる。
全てはアメリカに掌の上と考えるのは過大評価がすぎる気がします。
アメリカがそんな神の如き手腕を誇るならアフガン撤退であんな無様はさらさなかったでしょう。
もし、多くの専門家の予想通りキーウが2日で陥落していたら西側では民主主義は滅ぶのではないかと将来を悲観していたと思いますよ。
まるでアメリカが挑発して戦争を起こしたかのような言い方ですが、
実際はやりすぎな位にロシアに融和姿勢を見せ、どうにか侵攻を思いとどまらせようとしてましたよね。
プーチンが侵攻後に流す演説を撮影した後は「こっちは全部知っているから、やめろ」となりふり構わない情報公開までして、食い止めようとしていた。湾岸戦争の時とは状況が全く違います。
ロシアの海外資産を没収して軍事費にまわせば良い。そうすれば何兆でも可能だろう?ロシアもその覚悟で戦争を始めたんでは?
ネプチューンはいいミサイルだけど数が足りてませんよねぇ。
アジアの方に、いい地対艦ミサイルありまっせ。
ってなことにならんかな。
株価急騰となってるから記事に名前のある企業の株価を調べてみた(年始から現在の株価)
ロッキード 22%
ボーイング -25%
レイセオン 86ドルから97ドルへ8%か9%ほど上昇
ノースロップ・グラマン 15%
GE -20%
BAE 33%
L3Harris 11%
ラインメタル 154%
タレス 61%
STエンジニアリング 9%
ハンファ -3%?(31ウォンから30ウォンへ下落)
L3Harris 11%
欧州勢の値上がり幅が大きく米企業は思ってたより控えめ
俺が数年前から握ってるGEとか見るも無残な事になってるんだよな…
MHIやらIHIは脱炭素関係の事業もやってるせいか割と上がってる
軍需専業ならともかく、民生と並業であれば民の売り上げ比率も大きく
それらに比べたらウクライナ需要は微々たるもんな上に一過性の売り上げ
に過ぎません
それに昨今はサプライチェーンの崩壊やら、部品供給の過多な偏りが
慢性的な部品不足を引き起こして製造業の重しになっています。
トピックス的に買いが出たとしても、そう大きくは無いと思います。