日本も防衛産業界の売上と基盤維持のため、海外の防衛産業のように米国市場に進出して年間7,300億ドル/約84兆円の国防予算に食い込むというのはどうだろうか?
防衛産業界が苦境に直面している要因の1つは増額された防衛費が米国に流れて国内に還流しないこと
日本でも防衛産業の維持や問題点について取り上げられる機会が増えてきたが、海外メディアや専門家からすれば「年間430億ドル/5兆円以上も国防分野に政府が投資しているのに何故国内の防衛産業が衰退するのか?」と不思議に思っており、高額な装備品調達が米国からの輸入で賄われているため国内の防衛産業界に金が落ちないという指摘もあるが、この問題の根本的な原因は米国製装備品の調達にオフセットを要求していないため投資資金が国内の防衛産業界に全く還流されていない点だろう。

出典:航空自衛隊
非出資国でF-35を調達した日本、韓国、ベルギー、ポーランド、スイス、フィンランドの中でオフセットを要求しなかったの日本だけで、韓国は軍事衛星の提供と技術移転、ベルギーはF-35サプライチェーンへの自国産業界参加と保守業務受注で7億ユーロ以上の収益を確保、スイスは調達費用の約50%に相当する30.5億ドル分(内10.5億ドルはF-35A取得に関連する部品調達やサービスに関するLMからスイス企業への発注分)の相殺義務を確保、フィンランドはF-35フロントフレーム製造や自国向けにMRO&Uやエンジンデポを設置する権利を確保。
ポーランドはオフセットとしてF-35サプライチェーンへ参加を要求したもののロッキード・マーティン側はこれを拒否してF-16やC-130の整備拠点設置を提案、この提案に不服のポーランドはオフセット契約にかかる費用10億ドルを節約する選択を決定を下したが「F-35プログラムにオブザーバー参加できる2008年のチャンスを生かしていれば交渉結果は異なっていた」と後悔している。

出典:海上自衛隊 護衛艦まや
非出資国のオフセットとしてF-35サプライチェーンへの参加を認められる国(ベルギー、スイス、フィンランド)と拒否される国(韓国、ポーランド)に分かれるのは興味深いが、これはF-35に限った話ではなく米国製装備品を対外有償軍事援助(FMS)経由で購入する大半の国は何らかのオフセット(直接投資か間接投資かは案件によって異なる)を要求して調達に投じる資金の30%~50%を国内に還流させており、海外から見ると「高額な装備品調達を米国から調達しても相応の相殺義務で日本の防衛産業にも金が回っているのではないか」と思っているのだ。
しかし日本の米国製装備品の調達は対米貿易黒字の相殺として扱われオフセットを要求できないor要求しない可能性が高く、米国製装備品を調達すればするほど国内の防衛産業に回ってくる金が少なくなるという他国と単純に比較できない特殊な構造をしているため「日本もオフセットを要求しろ」と主張するなら対米貿易黒字の相殺を防衛産業に押し付けている構造自体にメスを入れる必要があるのかもしれない。

出典:JGSDF / CC BY 2.0
だからそこ防衛装備品の海外移転で防衛産業業界の基盤を維持する必要があるのだが、現行の国産装備品は自衛隊のみが使用する前提で設計されているため海外市場で求められるニーズに一致しない(顧客の要望に合わせて仕様を変更したり機能を追加することを想定していない)ので直ぐに大規模な受注を獲得するというのは難しいだろう。
還流しないなら海外の防衛産業を参考に年間7,300億ドルの米国市場に進出するという方法もある
そこで日本も海外の防衛産業のように米国市場に進出して年間7,300億ドル/約84兆円の国防予算に食い込むというのはどうだろうか?
参考:BAE seeks more in U.S. despite a few setbacks

出典:Public Domain M109A7の開発・製造は現在BAEが請け負っている
ブリティッシュ・エアロスペース/BAeは1997年に「国防予算の合計が米国の半分以下しかない欧州市場のパイを米国の3倍以上とも言われる欧州企業が取り合っている」と語り、2年後にマルコーニ・エレクトロニック・システムとの合併で誕生したBAEシステムズは2001年に米国事業の拡大を決断、当時の年次報告書の中でBAEは「米国市場は欧州市場の2倍以上で、最も重要なのは研究・開発分野への投資額が欧州を上回っていることだ」と述べて以降、幾つもの米防衛産業企業を買収(投資費用の合計は70億ドル以上)して事業規模を拡大してきた。
イタリアのフィンカンティエリも米造船企業を買収して米造船市場に進出、米海軍や沿岸警備隊の艦艇保守や小型艦艇建造など手掛けコンステレーション級フリゲートの受注に成功、オーストラリアのオースタルもオースタルUASを設立してインディペンデンス級沿海域戦闘艦やスピアヘッド級遠征高速輸送艦の受注に成功、ドイツのラインメタルも複数の米子会社を通じて地上車両やISRプラットフォーム向けのシステム開発、各種火砲の砲弾製造、無人プラットフォームの開発・製造で実績を挙げており、フランスのタレスも米子会社を通じて国防総省から米軍の通信機器やシステム関係の契約を受注している。

出典:U.S. Navy graphic/Released 米海軍が発表した次期フリゲート艦「FFG(X)」の完成予想イメージ
この他にも2021年に米国進出を果たしたシンガポールのSTエンジニアリングも民間航空会社や米軍向けの航空機整備拠点(MRO)の運営、沿岸警備隊向けの艦艇建造や米海軍の艦艇補修事業の受注などで20億ドル以上の売上(2020年度実績)を記録しており、韓国のハンファディフェンスも国防総省からの受注を獲得するためトップに米国人を据えた現地法人を設立して米企業との協力(オシュコシュと協力して米陸軍の次期歩兵戦闘車にレッドバックを提案中)を模索している最中だ。
日本も現地企業を買収するか新たに現地法人を設立して7,300億ドル市場に進出できれば防衛産業の基盤とも言える人材育成や雇用の維持が容易になり、国産の装備品開発に米国で得た経験を活かせるのではないだろうか?

出典:Australian Army
因みに米国に進出した海外企業の中でBAEの成功は群を抜いており、BAEだけは機密性の高い国防総省のプログラムに元請けとして参加する資格があるが、他の海外企業は元請けの米企業から仕事をもらうレベルでしか米市場に食い込めていない。
これは英国と米国の特別な関係を利用したという側面も勿論あるが、BAEは米国と締結した特別安全保障協定に基づき「米国国内での事業を請け負うBAEの現地法人は米国の法律に従い米国人を経営のトップに起用、本社からの完全な独立性=完璧な機密保持を確保している」ためで、BAEの現地法人は国防総省の機密にアクセスすることが可能だがロンドンの関係者に情報を漏らすことは禁止されており、仮に最高経営責任者からの指示でも機密保持に違反すると現地法人が判断すれば拒否できる強力な権限を持っている。
つまりBAEの現地法人は完全に米企業化することでロッキード・マーティンやボーイングと同じ扱いを受けられるが、恐らく国防総省のプログラムを通じて得られた情報や技術をロンドンにフィードバックすることは禁じられているのかもしれない。
出典:public domain ズムウォルト級駆逐艦3番艦「リンドン・B・ジョンソン」の建造風景(現在は進水済み)





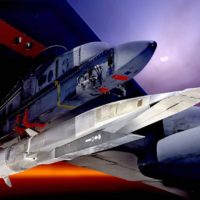






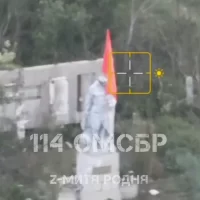








20小銃とか売り込んで見たら?
まー何でも果敢に売り込んで行こうぜ日本🗾
今はアジア唯一の工業国では無いのと、近隣諸国(中国、韓国)でも絶賛爆売中ですし、基本的に賛成です。
最初に売り込むのは水陸両用装甲車辺りでは?アメリカは予算超過で開発中止にされているし、共同研究しているし、可能性は高いと思いますよ。後は興味を持っていそうな飛行艇、US-2後継機を共同でやるとかもいけるかも?
沿海域戦闘艦のコンセプトのパクリで小型で必要人員が少なくて済む安い原潜(特殊潜航艇みたいなのをベースにミッションパッケージ(オプション船体付けたり外したり)で色々な用途に使える)とかでしょうか?母艦から運用する前提にすれば揚陸作戦も可能かも?
小銃はアメリカでM27(HK416)採用してるので、難しそうですけど相当頑丈でAKシリーズを超えるレベルであればオフセットで買ってもらう方法も有りますね、その代わりに大量のドローン買わされそうな予感が・・
アメリカ軍の新型水陸両用車は既に開発が完了していて発注も済ませているはずでは?
BAEのタイヤのでしょ、水上より陸上に特化したタイプ、海兵隊的にはキャタピラタイプのEFV(開発中止)のようなものも欲しいみたいですけど、そうでなければ共同研究なんかしてくれませんよ。
参考
リンク
最近のアメリカ海兵隊は少し規模を縮小してその分対艦ミサイル部隊やドローンの拡充を行うらしいので同じ用途の水陸両用装甲車を2種類も導入するでしょうか?
最近のアメリカ軍はお笑い要素満載なので、確実にこうなるとか言えなくないですか?例えば沿海域戦闘艦のうち最初に建造された4隻(LCS-1~LCS4)は、2021年に退役するとか、ストライカーMGS2022年退役とか、最新なのにどうして?とかね。ACV1.1もMRAPの水陸両用版という感じでアメリカがイラクに駐留時の事情で採用されている様なのと、人員輸送能力と水上速度はAAV以下なのでどうなるか分からないですよ。
参考
ACV1.1
リンク
ストライカーMGS2022年退役
リンク
インディペンデンス級沿海域戦闘艦
リンク
お笑いねぇ。
その言葉ホント好きだね?
ドローンは国産でマダム作れないのかな?
けどユーザーとしては攻撃用ドローンはある程度の量は欲し所ですね。
米軍の調達プログラムに食い込むことと、米軍の調達プログラムで数字を出すことと、米軍の調達プログラムで作った利益で日米間の収支赤字を補填するのは一致させられないように思います。
「いいものなら売れるというナイーブな考えは捨てろ」じゃないですけど、特に兵器市場は保護貿易志向でガチガチなだけに結局最後は市場を持ってる(軍事予算をつぎ込んでいる)購入者が優位な訳で、自動車産業がそうであるように米軍向けにいくら売ってもBAE同様に「現地法人が」「現地人を使って製造して」「利益は現地で再投資し」「現地で納税」するようになるのがオチだと思います。
それも意義あることですし、個人的にはBAE米国法人のような日本の兵器産業にとっての米国市場窓口になる半官半民の現地法人の設置には賛成です(共同研究などの拡大で国防費の節約になるし、共同開発した兵器を第三国に輸出する場合のパテント料も入る)。地方の雇用創生の面で結託している米国の議会と兵器メーカーに日本が正面から対抗していくのは困難ですが、幸いにして複数のロビー団体やシンクタンクを経由してワシントンには強いパイプがいくつも通っています。この場合メーカーや議会はどちらかといえばライバルに相当しますが、同じ行政機関として政府どうし軍どうしの連携の延長で開発プログラムの連携は模索できるんじゃないかと思いました。
兵器購入で積み上がった赤字は…別分野で取り戻しましょう!
つい昨日の他所の記事だけど防衛装備庁が米軍の整備体制に中小企業が参加しやすくするための支援制度を本年中に実施する方向で検討してるって話が出てたね
リンク
ここでも将来日本国内の防衛関連企業がグローバルなサプライチェーンに進出できるように米国企業からも支援体制が受けられるような制度作りをするみたいな事も書いてあるし、掛かる時間はともかく概ね管理人が言ってる通りの方向性を防衛省も目指してるように思うから、この分野で防衛関連企業を成長させていくためには米国の市場に上手い事絡ませるのが良いのだろうね
はぇ~…動きがあるようで良かった。
その記事、ちょうど昨日見たばかりだったので貼ろうと思ってた。
防衛省も無策というわけではないのでしょうが、国内防衛産業の維持のための大きな方針も考えた方がいいんでしょうな。
企業側が長期的にリスクを取って動きやすくなるような。
沿岸警備隊向けの艦艇建造やら地域整備なら三原則時代でも出来た筈なんだけどね。高速鉄道とかみたいに噛み合ってる事業もあるが、結局は得られる筈のチャンスも手に行く気が元から薄いという事なんだろう。デュアルユース反対とかGPSの果実受けてる連中が言う国だからな
少なくとも、企業にやる気を出せというのは無理があるでしょうね。
殆どの企業は防衛関連で儲けようなんて思ってないでしょうし、本業に影響するほど業績が悪化するなら、撤退すればいい話ですから。
そもそも防衛部門はどの企業でも利益が出ないorほとんどないから肩身が狭い思いをしてます。
海外進出のために投資してくださいなんて声を上げることはほぼ不可能。
これから先も、自衛隊向けガラパゴス装備を作りたいなら、政府や防衛省が何とかすべき。
まぁ、固有要件の精査と妥協ができない”彼ら”のせいで、日本の防衛産業に未来はないでしょう。
ロサンゼルス級原子力潜水艦の整備を日本企業が受注できんか。
アメリカも困ってるみたいだし、オーストラリアも中古艦がほしいだろうし、アメリカやオーストラリアの企業と合弁で原潜整備会社をまずはアメリカで立ち上げ、ゆくゆくは建造にも乗り出すとか。
機密の問題で日本国内で受注するのは不可能なんじゃない?
BAEみたいに米国に進出して米国の法律に従う現地法人なら受注できるかもね。
賛成です。
戦後の航空産業もそこから復興しましたからね。
とはいってもいろいろとありましたけれど。
防衛産業というより武器に対する日本人の意識が変わらないと無理でしょうね。
只の物として扱えばいいのに、人の命を絡めるからややこしくなる。
ほっといてもタヒぬのにね。
人のいのちを考慮しない社会ってのもわれわれ庶民には生きづらいと思うけどな
例えば中国みたいな
>人のいのちを考慮しない社会
似た言葉に「他国人の命を考慮しない社会」ってのがあるぞ、たとえばアメリカみたいな。
それが足引っ張って防衛産業、ひいては日本国に不利益を与えるんだから、いったん無視すればいい。
理想も理念も余裕がないとどうしようもないから。
せっかく米国外唯一の空母母港持ちで米艦船のメンテナンスにも携わってて米軍装備導入しまくってるんだから、米軍で問題になってる艦船補修事業に食い込んでいけそうには思える
装備品の売り込み合戦とそういうサービスの売り込み、実際のところどっちの方が大変なんだろうね?
結論から言うと不可能
国から仕事を降ってもらうだけの日本の「子供部屋おじさん防衛産業」には、百戦錬磨の外国企業に勝てる様な技術も無ければ、海外に販路を広げようというチャレンジ精神も無い
このままジリジリと衰退していくのが自然な流れだろう
だからそこに食い込めるように頑張ろうぜって話なのに頭ごなしに否定しちゃ駄目でしょ
頭ごなしにってw
昭和から令和の現在まで親の脛を齧って生きながらえてきた、ニートの子供部屋おじさんに対して「まだ本気出してないだけ」「これからだ」なんて言っていたら笑い者だろう
長い間、甘えた環境にいたニートがこれから通用するだとか現実が全く見えていない
そんな状態からでも小さい仕事でもなんでも出来そうなことを見つけてやっていこうってしてるとこなのに、お前には無理諦めろはないでしょ。
あんた見たいな、敗北主義の、ニートがー、って言ってる人は一人で壁に向かってブツブツ言っててよ。
今からどうにか頑張って行こうと、思ってる人の足を引っ張らないでくれ。
言うて在日米軍相手のサービスは既にやってるからね。
ニートではなく内職だな。
親の用意してくれる内職やってるだけじゃなくて、
同じ仕事を親の会社に出社してやってみろ、程度の話。
武器輸出を官が仕切る(縛る、足枷する)って今の構図ではダメでしょうね
決して民に力が無いとは自分は思いませんが、企業イメージを損なわない様に
かつ国の顔色を伺いながら、政治的な介入を受けながらでは、民主体で輸出に
積極的に活路を見いだそうとはしないでしょうし、出来ないでしょう。
軍事=悪の意識はもはや日本固有の文化です、武器輸出をただのビジネスと
ドライに割り切る文化はこの国にありません。
諸外国の軍事メーカーも政治的な介入は少なからず受けます、ただ日本はそれら
とは違う特殊性があります、この国で長いあいだ武器輸出を実質禁止して来た
思想的な背景にあるものが何かです。
自衛隊は違憲、軍隊の保有は平和憲法に反する、日本が武器輸出大国(=武器商人)
になるなどもっての外、世代変わりして来て昔よりも軍事アレルギーは弱まったと
は言え、いまだ根強いこの文化をいつまで引きずるのか、あと何世代待てばいいのか
どうすりゃ早く変われるんだって思います。
いっそ北朝鮮に核の一発でも落としてもうらうか、そうすりゃ政治家から国民まで
頭から尻尾まで防衛意識が変わるだろうと思ったりもします、自力で意識改革が
出来なければ、日本人が変わるには第二の黒船が必要でしょう。
それをどうにかしようとしてるのでは?
まずは構造改革でしょ
黒字分を相殺するために防衛産業を犠牲にするのはやめよう
黒字部分は国債を買い増したりアメリカ産ガス購入増やせばいい
外交の観点だと「貿易黒字を相殺しつつ米国の優秀な製品が手に入る一石二鳥のシステム」
国防の観点だと「膨大な金額と共に国内防衛産業が消えていく悪夢のシステム」
と正反対に捉えられるのが複雑なところ。
頑張ろう日本
日本は戦後何十年も武器輸出をしてこなかったから、私のような一般人にとっては完全に浦島太郎状態。
日本は米国に優遇されうまいこと最新兵器を回してもらってると思ってたし、輸出を解禁したら日本の潜水艦を売って欲しいと話が次から次へと舞い込むものだと思っていたが、、、
頭の堅い老兵は消えるしかないのか、、、
大切なのは国が動こうとしてるときにろくに調べもせず批判したり反対しないことだよ。
ある程度調べて、日本のためになりそうなことだったら応援しよう。
否定する気は無いんだが、おそらく大変に高いハードルがあるだろう、
世界最強米軍の要求を充たせるような高い技術のみならず、あの国が取引においてシビアな点も
日本の防衛産業には試練だね
トヨタのランクル(ミリタリーグレード)ならアメリカでも売れるんじゃないでしょうか(つうかランクルもう売ってるし)
まあ米軍はジープの方が強いかもしれませんが
それと似たようなのがハンヴィー(製品化の流れが逆で軍用車から始まったけど)。
想定されていなかった戦場に投入→装甲の脆弱性が問題に→装甲強化→てんこ盛り仕様
になってJLTVが導入されたから、ランクルも同様に装甲等の武装車両としての能力不足が問題になると思う。
貿易収支のバランスを取るために、兵器の他にアメリカから買える物って食料品と石油(シェールオイル)しか思い浮かばんなあ。
NTTが営利になるところしかやりたがらない公衆無線LAN機材一式とか