読売新聞は7日「オーストラリアの汎用フリゲート導入に関して日本政府は共同開発を検討している」「既に防衛省は三菱重工業などと非公式の協議を始めており、豪政府が求めてくる装備や機能を追加したもがみ型ベースの艦艇開発を検討している」と報じた。
参考:オーストラリアの新型艦、政府が共同開発を検討…海自の最新鋭護衛艦輸出を想定
日本が豪海軍の汎用フリゲート受注戦で勝率を高めるなら、海外企業と手を組むのが最善なのかもしれない
アルバニージー政権は海軍再編に関する分析結果を今年2月に発表、この報告書は政府に「水上艦戦力を2倍に増やせ」と勧告しており、具体的にはハンター級フリゲートの取得数を9隻→6隻、アラフラ級哨戒艦の取得数を12隻から6隻に削減し、有人運用も可能な大型無人艦(6隻)と汎用フリゲート(11隻)を取得するよう勧告している。

出典:Navantia Alfa3000
汎用フリゲートの取得はアンザック級フリゲートの後継艦を想定しており、報告書は検討候補にドイツのMEKO A-200、スペインのAlfa3000、日本のもがみ型、韓国の大邱級BatchIIもしくはBatchIIIを挙げていたが、アルバニージー政権が勧告に従うかどうか、仮に従った場合でも汎用フリゲートに対する要求要件や調達スケジュールなどは一切不明で、この報告書も汎用フリゲートの調達について「海外で3隻、西オーストラリアで8隻建造すべきだ」としか勧告していない。
それでも検討候補に名前が挙がった韓国のHanwhaは「米造船業界への投資」を兼ねてAustal買収に動いており、Austal側も「豪海軍や米海軍の元請け企業としての立場、防衛契約に関する所有権事項を考慮するとHanwhaの買収案は豪米当局から承認される可能性が低い」「Hanwhaが豪米当局の承認について追加の確実性を提示できれば当社はさらなる関与に前向きだ」と含みを持たせているため、もし買収が成立するとHanwhaは汎用フリゲートの受注戦で著しく有利になるだろう。

出典:HD Hyundai Heavy Industries FFX-III
現代重工業もGE Aerospaceと「輸出向け艦艇に最適化された推進システムの共同開発」で合意、現代重工業はグローバル市場向けの艦艇設計・建造を、GE Aerospaceは同艦艇向けのガスタービン供給を担当し、輸出向け艦艇のMRO事業やオーストラリアが調達を検討している汎用フリゲートなどでも協力する構えだが、日本政府も汎用フリゲートの受注戦に乗り出すらしい。
読売新聞は7日「オーストラリアの汎用フリゲート導入には日本、スペイン、韓国、ドイツの艦艇が導入候補に列挙された。年内にも具体的な要求性能などを明らかにし、各国に共同開発を提案すると見られる。既に防衛省は三菱重工業などと非公式の協議を始めており、豪政府の対応を踏まえて検討作業を本格化させる方針だ」「防衛省は豪政府が求めてくる装備や機能を追加したもがみ型ベースの艦艇開発を検討している」「日豪で艦艇を共通化すれば相互運用性と抑止力の向上が図れる他、国内の防衛産業への経済的効果も期待できる」と報じた。

出典:海上自衛隊
さらに「日本はオーストラリアの次期潜水艦受注を逃した経験があり、汎用フリゲートの導入候補に列挙されたスペインと韓国には豪軍装備品の開発に関わった実績がある。受注競争は激しくなると見られ、日本政府はライバルとなる3ヶ国の動向や提案内容も注視する構えだ」とも指摘している。
豪シンクタンクの米国研究センターは今年3月「汎用フリゲートの取得は日本製フリゲート艦を取得すること上手くいくかもしれない」と言及したことがあるが、日本製フリゲート艦のデメリットについても「海外輸出の実績が殆どない」と指摘したことがあり、Hanwha Oceaはカナダ海軍の潜水艦受注に向けてBabcockと提携した際「同社の豊富な海外事業経験とプロジェクト管理能力はポーランドやカナダでの受注競争において当社の力になるはずだ」と言及した。

出典:Hanwha Ocean
もし日本が豪海軍の汎用フリゲート受注戦で勝率を高めるなら、海外での防衛事業、防衛プロジェクトの管理能力、軍艦の現地建造やサプライチェーンの構築にノウハウをもつ企業(例えば導入候補に列挙されていない英国のBAEなど)と手を組むのが最善なのかもしれない。
関連記事:豪シンクタンク、もがみ型の取得で海軍再編が上手くいくかもしれない
関連記事:オーストラリア海軍の再編計画、汎用フリゲートの検討候補にもがみ型が浮上
関連記事:豪州が海軍の戦力構造を小型艦中心に変更か、ハンター級が削減の対象に
関連記事:韓国のHanwha、米軍プログラムの元請け参加が可能なAustal買収に動く
関連記事:現代重工業がGE AerospaceやL3Harrisと提携、豪海軍や加海軍の受注戦で協力
※アイキャッチ画像の出典:海上自衛隊





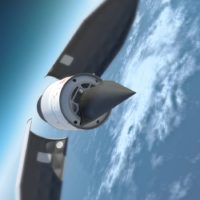


_R-1-200x200.jpg)












何事も経験。
今回駄目だったとしても次に繋げてほしいですね。しかし本気で輸出するつもりなら韓国並みに政府が後押ししないと厳しいんじゃないでしょうか。
それ以前にオーストラリア軍の要求がどこまでで
産業界はどこまで妥協できるかじゃあないかな?
政府の後押しも重要だけど、潜水艦でも一番問題になったのは現地生産だから、BAEがオーストラリアに子会社もってたら協力できたらいい感じになるかも。
どうせ日本は完成品の兵器輸出ができないから、初めの三隻だけ日本で船体を作って現地で艤装すればいいんじゃない。その後の艦艇は現地生産で。
潜水艦と違って、技術力もあまりいらないし、秘匿技術もすくないしね。
韓国と同等なのかは分かりませんが、日本政府の後押し制度はありますよ。
同志国に対する現地設備投資等のオフセット契約にはOSAの枠組みを活用できるかと。無償資金協力なので開発途上国対象が原則ですが、「我が国及び地域の安全保障上のニーズや二国間関係等を総合的に判断して対象国を選定」することになってますので豪州にも適用可能と思います。
防衛基盤整備協会基金から防衛装備製造等事業者に、対象国向け仕様への設計変更等の費用を助成する制度もあります。
政府の背中を刺して来る公明党の排除も必要かと
まず政府の後押しとか言っている時点で終わっている。本気で輸出するつもりなら頑張るべきは対お客の対応をするメーカーの方。政府の支援はメーカーが一部国民の反発上等で兵器を何としてでも輸出するやる気を見せた後の話で、やる気がないヤツに公金つぎ込んでも無駄になるだけ。
オーストラリアの希望がどんな物なのか分からないけど、現行型でさえもがみ型船体サイズは各国候補の中で1番大きいからダウンサイジング希望してきたら?底部の小型ソナーでは無くバウソナー搭載を希望したら対応するのか?特徴であるUNICORNが要らないなら再設計するのか、もしくは中の機器を入れ換え希望した場合にその電波干渉の試験をやり直すつもりはあるのか?
OAX-3光学複合センサーは信頼ならんからL3Harris光学センサー積みたいからインテグレーションするのか。正直な話、日本国内になるべくお金落としたとかやましい考えしているならやめた方が良いと思う。
>正直な話、日本国内になるべくお金落としたとかやましい考えしているならやめた方が良いと思う。
他国への慈善事業をしているわけではなく、商売をしているのだから利益を上げなければ意味はない。
日本国内にお金を落とすことがやましいと考えるのなら、商売自体を辞めたほうが良い。いったい、なんのためにオーストラリアへ売り込むんだい?
現状、本邦の防衛装備品・技術海外移転事業は全て、防衛装備移転三原則運用指針に則り厳格な政府管理下で行われるのが原則です。
企業が勝手に入札参加したり、勝手に海外企業と提携又は協業し防衛装備品を開発・販売したり、勝手に提案や交渉等の受注活動を行うことはできません。
更に、5類型外である護衛艦は次期戦闘機のような政府管理下の共同開発事業でなければ海外移転できません。入札方式であったとしても、落札後に(形だけでも)そのような事業形態を取れない前提では入札参加もできないことになります。
先方の要求仕様・条件に応えられるか、官・企業間で検討を重ね総合的に可と判断されれば、事業参画に向け必要な事前作業や必要ならば相手先等との交渉に入ることになります。企業側のやる気が試されるのはその段階ですね。
もがみ型の基本設計をベースに要求に応じた改設計を行うことは一定の範囲内なら可能ですよ。
現にMHIは胴体を短縮した哨戒艦型と沿岸警備隊型の構想を公開しています。逆に要求に応じた大型化も可能でしょう。
日本が海外と組んでフリゲートの輸出に乗り出したら海外に技術が盗まれるとか憲法違反だとか色々言ってくる人はいるでしょうね。
他国も日進月歩なので、いずれ盗まれるか追い付かれるかだけなんですけどね。
というか、日本が盗み、追いかける側でもあるということ理解していないと、ガラパゴスにしかならないという。
少なくとも輸入や共同開発など、海外の技術に正規な手段でアクセスするというのは国内技術の養成にも必要。
競合他社の存在がない状態で企業努力を継続できる企業というのも少ないし、継続的に新技術や新体制の取り込みをしないと世界に置いてきぼりにされてしまうので。
>憲法違反だとか
早くも見かけましたよ
GCAPでもギャンギャン騒いでましたし
まぁあの手の人たちが騒いで政府が方針を変えることは無いでしょうから、無視で良いんでしょうけど
ただ不採用だった時に「私たちの力だ!」みたいな勘違いをやらかしそうです
潜水艦の時に技術が盗まれる云々で反対意見が強かったのは「結果的に日本の潜水艦の性能が露呈するから」でしょうから、隠し事なんか無いに等しい水上艦でそんな話はあんまり出ないかと。
もがみ型のファミリー構想がここになって出てきましたね。元々輸出を考慮した艦なのかな?と思ってましたがやっぱり三菱をやる気なんですかね。これからの武器輸出に繋がるためにもまずは経験しないといけないですし、頑張って売り込んで欲しいですね。そう言えばもし成功したらオーストラリアだと何型って言われるんだろう。MOGAMIと言われる事は無いだろうけど
Best級にしよう
これは、とても楽しみですね。
日本は円安なだけでなく、造船業・造船関連産業の集積が残っていますから、有効に使って欲しいですね。
Quad,AUKUS2と日本は政治的には有利なのでここは頑張ってもらいたいところですね。
現地企業との協業が鍵になるのは確かですね。
潜水艦ほど高度な製造技術を求められるわけではないので、現地建造の敷居も低くなりますし。
現地建造分についても、やらかしそうな減速機周りは当初は日本から輸出した方が良いかも知れませんが。
CODAG方式は、ガスタービンとディーゼルの回転数差が大きく、減速機への負荷が大きいらしいですから。
あとオーストラリア海軍は、毎度仕様をまとめる段階で要求が過大になってズルズルいく癖がありますので、なんでも出来ます的なプロモーションは、過去の失敗の轍を踏むことになります。如何にうまく、仕様面のトレードオフ関係と技術的な限界をコンサルする能力が重要になるのでは無いでしょうか。
ちなみに候補に上がっている艦のうち、韓国の大邱級を除く艦はすべて長船首楼型の船型で乾舷をかなり高く取っていますし、シアも強いですね。多分このくらいの大きさの艦が、外洋での行動中に艦首側の武器を確実に使えるようにした場合、容積的にも有利なこの船型に落ち着くんでしょうか。この場合、復元性を確保するために上部構造物の高さを抑える必要が生じますので、レーダーの搭載位置やサイズにも制約が生じます。その辺りがデメリットでしょうか。
小規模カスタマイズでないと流れると思う。
あさひ型護衛艦が建造されていた当時は、「このまま護衛艦の高額化が進んだら、2年に1隻しか護衛艦が建造できなくなる」
なんて言われていたのに、あきづきより高価な改もがみ型を一気に12隻も建造、しかも海外に大々的に売り出すなんて、平成の自分に言っても信じないだろうな
時代が変わり過ぎている…
オーストラリアのことだから、英国に倣って、電気推進を求めてくるのでは。
将来的に必要な電気を予め確保するとか言って。近い将来のレーザー砲とかを考えると。
もしそうなら、日本のもがみ型の場合、動力部分で結構な変更が出るのでは。
素人は、推進と発電は分けて考えた方が良いのでは、と思うのだけど。
必要なら、上構内に発電機を増設する方が良いと勝手に思っているのだけれど。
潜水艦用ドッグと違って、フリゲート艦のような軍用水上艦用の建造ドックの¥に余裕があるようですね。
輸出実績というか実戦経験も必要なんでしょうね。
スペックが高くても実戦では色々不具合が出るもんですし。
そうなるとどうしても不利になりますね。
海戦の実戦経験なんてどこもほとんど無いかと。
艦艇が試された戦いなんて第二次世界大戦以降だと1982年のフォークランド紛争といまのウクライナロシアくらいでしょ?
24/5/2のハワイでの日米豪3か国の防衛相会談である程度方向性が出たのかな?
共同声明の中に協力の拡大として
運用に係る先進的な技術分野において、研究、開発、試験及び評価(RDT&E)プロジェクトに関する日米豪取決めによる協力機会を追求する。
とあるので、もがみ型をベースに何か設計・建造する可能性はあるかも。
日本が受注できるかどうかは別として、2030年代就役の新型フリゲート品評会だと思うと興味深い。
省力化、戦闘の自動化、多用途化がトレンドだろうが、各国がどんな提案をしてくるか楽しみ。
特に、コストがかけられないこのクラスの戦闘艦でどのような戦闘システムが搭載されるか。
コストと性能のバランスが問われそう。
もがみのニョキっと感は中々・・・それはそれとして建造費500億ってのは艤装込みなのかな?結構お安く作れるのね。
オーストラリアがかなり省人化をかなり重視しており、この点でリードするもがみ型はなかなか有力なんではないでしょうか。
スペインはホバート級建造でオーストラリアとの関係が既に構築されているのが強みなんですが、候補になってる艦が小さ過ぎるのが気になるとこですね。
この動きは極めて危険であり日本とアジア諸国の関係を悪化させます。今の豪州は反中政策に狂奔しており、この戦艦は中国を攻撃するために使用される予定です。そんなものに日本のお金や資源が使われるのは容認できません。断固反対だ
戦艦呼ばわりにはもう突っ込みませんけど、金を払うのはオーストラリアですねえ
こんなところにまで中国の代理コメントがなされるとは…
そんな意見いらないよ。
改もがみ型じゃないのか
もがみはあくまでベースだから、上手く売れてもかなり違う艦になるんじゃないかな
今のままじゃVLSも無いし
FFMの装備品のうち殺傷兵器に属する国産装備は07VLA、17式SSM、専用小型機雷くらいですが、豪州海軍は全部不要と見なしそうなので純粋な艦艇+システムの輸出(火砲などは向こうで別途ポン付けしてもらう)は現時点の法制でも可能そうではあるんですね。FCSとか本当に大丈夫でござるか~?って気もしますが…
しかしFFMは本国向けでも順調に価格が上がって、新型だと600億近いんですよね。豪州側が青写真で出してるプログラムコストを11で割ると500億弱でも、全部を艦艇建造に回す訳ではなく豪州産業界への投資が何割か含んだ予算なので、省力でも駆逐艦並のサイズ感があるFFMベース案はこのまま行くと予算超過で着られそうな気も(こういう時こそ豪州の造船業界への技術支援のような国ぐるみのオフセットを使うべきなのかもしれませんが)
フリゲート艦は決戦兵器ではないですし、今のフリゲート艦の今の性能の中枢はソフトウェアとセンサーなんでブラックボックス化もし易いですし輸出は良いと思います。
気になってるのは、兵器を輸出するに当たって日本は何を考えて輸出するのかという姿勢が気になりますね。
韓国はモロに兵器輸出で経済的利益を目指しているように見えますが、日本も経済的な利益を目論んで今後輸出に舵を切るのであればちょっとおかしな方向に進んでると思います。
今回は豪ですが、西側の血の結束と言えば言い過ぎですが、結束力を高める為に武器も回しまっせという意図での輸出であれば大いにありと思います。
過去にも書きましたが経済的な利益を目指すのであれば生産量を一定に保つ為に国際関係が安定して軍事需要が減る場合需要を掘り起こす為に国際関係が揺らぐように不必要な緊張を高めるような国際政治が必要になってきます。
それは今のスーダン内戦みたいな事を発生させるように、若しくは発生した他国の内戦に割り入って両者を煽って武器を売るみたいな日本が築いた道徳的な優位性を捨てるような振る舞いになってきます。
日本は経済が衰退していますのでコストダウンという経済的便益の為に武器輸出のインセンティブが高まっていると思いますが、それは日本が30年以上、的確な成長戦略を作れないという国家の根幹の問題から目を逸らした悪い方の対症療法と思います。
国が経済成長し続けていれば今後も最新兵器を自前の分だけをコスト高で作る余裕が作れます。
そしたら、輸出する場合でも、それは自国の外交安全保障的に意味のある時だけ輸出するという正常な判断での「健全な武器輸出」だけを行えます。
今の防衛装備が不足していたり、防衛増強が日本経済に対して重い負担になっているのは国の経済が成長出来ていないからであって、武器輸出をしてこなかったからではありません。
潜水艦など技術流出した場合、日本の防衛の根幹が脅かされてしまうような兵器以外の輸出は構わないと思いますが、それは韓国のような経済的便益の為であってはならないと思います。
何百何千の輸出が見込める地上車両や銃火器類ならともかく、高々数隻程度の艦で経済的な意図は全くないと思う
日本が豪州に武器輸出に積極的なのは、ひとえにダイヤモンド構想の為だろう
日本のシーライン的にも豪州は重要区域だし、よっぽど日本が損しない限りは、ある程度手厚く扱うのはおかしくないよ
これはインドにも言える
2024年3月に軍艦島ツアーで三菱重工業長崎造船所をフネで通りましたが、もがみ型FFM2隻が浸水済み・艤装中でそれぞれ、FFM-5やはぎ、FFM-6あがののようでした。
FFM-7によどは進水済みですが、確認できた記憶がないのですが、もしかすると2隻の後ろに接岸していた可能性もあります。
海自のプレスリリースでもFFM-5以降の就役はまだっぽいので、三菱重工業長崎造船所のもがみ型FFM建造キャパはギリギリかもしれません。
三菱重工マリタイムシステムズ (旧:三井E&S造船 玉野艦船工場) も発注は1隻ずつのためこちらも増やせるのかどうか微妙ですね。
そういう意味でも、海外と組んで建造するのは保守・メンテや生産キャパの問題を解消するために必要かもしれません。
ただ、仕様変更はナシか、カスタマイズに関する条項は制約をつけないと、もがみ型FFMを海外に提案する価値は少なくなりそうです。
日本はアングロサクソン同盟諸国と兵器開発運用でも連携強化しないと中露朝韓に離島
領海世界6位のEEZを軍事力で奪われてしまいます。
主権国家の原則に従って現状と乖離した憲法から改正し兵器開発輸出の法律を整備しなけ
れば平和を騙る内外の反日勢力が現憲法を根拠に妨害工作をし続けるでしょう。
仮に最上型が採用されれば海自と豪海軍でネットワークをリンクするんですかね。
ネットワークリンク出来るのであれば準同盟も深まりそうですね。
「殺傷能力ありますよねダメダメ。どうしても輸出したいなら相手国あれこれ条件縛り付けて我が党の認める平和仕様じゃないと合意しませんよ」
物は経験として、オーストラリアの事ですし、何処と契約しても後から後から仕様変更の追加要求出してきそう。
アメリカのコンステレーション級も8割再設計?でグダってそうですしどうしてこうなるのやら。