米国務省は28日「日本にJASSM-ERを売却する可能性を承認して議会に通知した」と発表、承認された1.04億ドルの売却内容には最大50発のJASSM-ERや関連費用が含まれているため、1発あたりの取得費用は208万ドルとなる見込みだ。
参考:JAPAN – JOINT AIR-TO-SURFACE STANDOFF MISSILES WITH EXTENDED RANGE (JASSM-ER)
導入するJASSM-ERはF-15J改修機だけでなくF-35Aでの運用も視野に入っているのだろう
米国務省は28日「日本にJASSM-ERを売却する可能性を承認して議会に通知した」と発表、承認された1.04億ドルの売却内容には最大50発のJASSM-ERや関連費用が含まれているため、1発あたりの取得費用は208万ドル(米空軍が2024年会計年度に取得するJASSM-ERのコストは128万ドル)となる見込みだが、米国務省の通知は目安なので実際の契約内容や金額はロッキード・マーティンとの交渉で決定され、この売却に関連して提案されたオフセット契約はない。

出典:ロッキード・マーティン JASSM-ER
防衛省はF-15Jの改修機にJASSM-ERを搭載する予定だが、米国務省は「提案されている売却はF-15J含む空自の戦闘機に先進的な長距離攻撃能力を提供することになる」と言及しているため、F-15J改修機だけでなくF-35Aでの運用も視野に入っているのだろう。
因みにF-15J改修の初期費用高騰について財務省は「防衛省が防衛所要上の必要性を拠り所に日本独自仕様の装備品取得=実質的な開発を進めたが、米空軍が採用していないLRASMやDEWSの搭載を要求したため初期費用が約980億円から約2,180億円に、改修費用の単価も約33億円から約49億円に、事業費用の総額(初期費用と改修費の合計)も約3,240億円から約5,520億円(約2,290億円増)に高騰し、プロジェクトの大幅見直しを行う事態になった。対艦ミサイルの運用をF-2代替することになった結果を踏まえると計画段階で各アセットの役割や費用対効果等を検討するなど今回の教訓を活かす必要がある」と指摘している。

出典:ロッキード・マーティン AGM-158C LRASM
防衛省はLRASM導入を見送り、DEWSをEPAWSSに変更することで初期費用を約1,600億円、改修費用の単価を約35億円、事業費用の総額を約3,980億円(約1,540億円減)に圧縮したが、2019年の事業開始時点で米空軍は保有するF-15C/DやF-15EXにDEWSを採用しておらず、カタールが発注したF-15QAもDEWSではなくTEWSを選択、米空軍がEPAWSSを採用するF-15EXの調達を決めたのは2019年(2020会計年度予算)なので、結果論から言えば「DEWSをパスしてTEWSからEPAWSSに進む流れは見えていた」と言えなくもない。
米空軍はF-15EへのLRASM統合を予定していないためF-15J改修へのLRASM統合は完全に日本独自の仕様で、総事業費用を2,000億円以上も見誤るというのは装備調達のプロとして流石にどうなのだろうか?

出典:Photo by: Master Sgt. Tristan McIntire AGM-158B JASSM-Eを搭載したF-15E
防衛省整備計画局長は参議院決算委員会で「日本が改修したF-15Jに統合予定のLRASMについてソフトウェアの改造費用や検証テストに必要な模擬弾購入費用を要求されている」と発言しているため、防衛省側はLRASMの統合費用を初期費用に含めていなかった可能性もあり、財務省も「スタンド・オフ・ミサイルの運用構想はどうなっているのか」「米空軍のプログラム=F-15に米海軍のプログラム=LRASMを統合する実質開発を選択したのか」と指摘している。
LRASM統合に必要な費用が幾らだったのかは不明だが、戦闘機に兵器を統合するためには当該兵器を制御するためのプログラムをミッションコンピュータにインストールして完了という訳ではなく、地上に駐機させた試験用の機体から何度も切り離し実験を行いデータを収集して飛行中の戦闘機から安全に切り離すことができるかを検証、この地道な過程を経て飛行中の戦闘機から実際に切り離し実験を行い「問題ない」という判定を獲得できれば統合が完了する。

出典:ノルウェー国防省 JSMの切り離し試験を行う特殊試験機 AF-01
但し、この検証は兵器を搭載する全てのハードポイントで行う必要があるため地味に手間がかかる上、これを検証するにはデータ収集用に改造された特殊試験機(F-35ならAベースのAF-01など)を用いなければならず、複数回行われる切り離し実験や試射に使用する模擬弾や実弾も必要になる。
圧縮された約1,540億円はLRASM関連の費用だけではないと思うが、最初から「5,520億円」に近い数字を提示していれば「防衛所要上の必要性があった」という主張にも説得力があっただろう。
関連記事:防衛省はLRASM統合を見送りF-15J改修を継続、来年度の予算に費用を計上予定
関連記事:米空軍の2023年調達コスト、F-35Aは1.06億ドル、F-15EXは1.01億ドル
※アイキャッチ画像の出典:Lockheed Martin

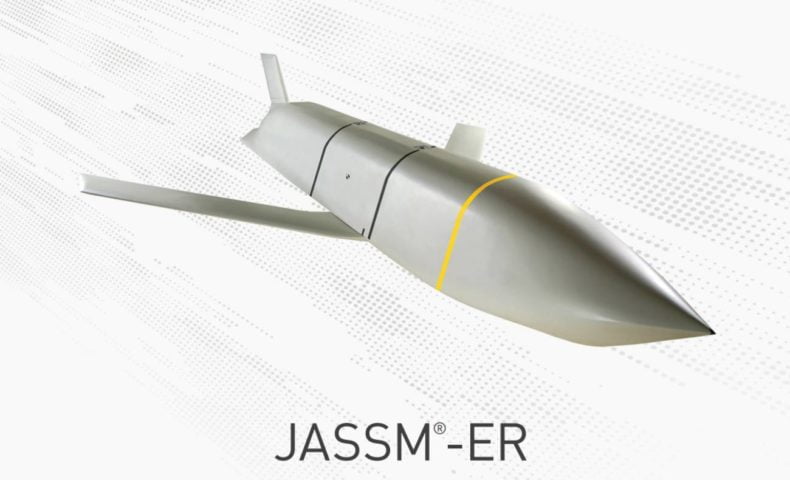



















私も予算策定とかしますが、固定資産や経費申請で2000億円解離があるとか最早誰も相手にして貰えなくなると思います。
予算を小さく申請して、実際には莫大な費用を計上させたり、必要とされていた機能をなくしたりするのは、経営者や株主(この場合内閣と国民)の判断を妨害する背信行為です。
不作為であればしょうがないが、防衛省はこの手の話があまりに多いので意図的しか思えない。
前もどっかで書きましたが、なんでも左翼と憲法と財務省と予算のせいにしてれば良いわけではない。
防衛省自体に大きな問題があり、自身の問題に向き合って欲しいです。
小さく生んで大きく育てる、公共事業でよく言われますよね。
当ブログの熱心な読者ならアタック級取得の顛末を存じてるかと思う
オーストラリアがアタック級を取得する際に起きた出来事で、数年と経たずに当初の約束の倍額を請求し納期の遅延もかまして来たフランス側にオーストラリア側が愛想を尽かしてオーカス級に乗り換えるやフランス側が裏切りと非難した事件
こういうことが日常的に起きるのがこの業界
結構少ないと思うんだけど…足りるのかな?
自衛隊が装備調達のプロであった事がどれだけあっただろうか。アパッチは揉めに揉めて不本意な結果で終わっているし、84mm無反動砲(B)も後継のM4出た後でも導入しているし古い84mm無反動砲の半分すら導入していない。UAV導入は他の国と比べて熱量は少ない。
日本の防衛組織は調達がろくでもないから輸出に関してもそれを引きずっている感じはする。
全部陸自さんの案件じゃないですかヤダー!
自衛隊の装備調達や開発に構造的問題があったのは明らかですが
そう言った問題を改善するために防衛装備庁が設置されたんでしょう
LRASMに関しては射程において一時期かあるいは今でも妙な誤解が広まってる傾向があった
それとは別に、現在のアメリカの武器外交の様子を見るに取り敢えず手を上げて主張せねば供給がいつになるか不明あるいは大幅に遅延更には取引が無効になる事例が増加
このような状況では必要不必要が不明なモノに対して取り敢えず要求するということはありだと思われる
LRASMの件に関しては軍事まとめレベルの知識でも防衛省の職員ってなれるんやなって思ったわ
医者じゃなければ厚生大臣になれない訳でも、検事や弁護士じゃなければ法務大臣になれない訳でもない
シビリアンコントロールだから軍務無経験の文民でも軍の上には立てる
自衛隊贔屓になるあまり財務省悪玉論に陥るのは結構ですが、防衛省の見積もりが毎回ザルすぎて指摘されてるという現実を直視した方がよいのではないですか?
今回の指摘についても至極真っ当にしか思えませんがね
リンク先のプレスを読むとさり気なくAGM-158B/B-2 、B2の文字が
これはポーランドが欲しがっていたJASSMXRで射程と弾頭重量が倍になったというアレのことか
だとするとERより能力が段違いなので価格の高さも納得
閣議決定された政府計画なので、財務省も国家防衛戦略と防衛力整備計画に明記された内容を無視できません。立場上予算圧縮の努力を要求してくるのは当然ですが、予算枠内に収めるために要求の撤回・削減や先送りを取捨選択決定するのは要求省庁の責任です。
財務副大臣をされた方から聞いた話ですが、予算折衝では優秀な財務官僚を論破可能な理論武装が必要だそうで、その準備と能力は省庁によってかなり差があったそうです。
JASSM-ERですけど、全長が4.27mと、ウェポンベイに格納できるAMRAAM(3.65m)や、JSM(Joint Strike Missile)(3.7m)に比べるとかなり大きいので、F-35で運用するとなると、ハープーンミサイル(3.85~4.44m)と同様、主翼下に搭載する形となるでしょうから、ステルス性が損なわれるのが悩ましいですね。
まぁ、JSMはまだ開発中なので無いモノねだりな話ですけれど。