米メディアのDefense Oneは3日、米空軍が極超音速兵器の試射に躓いているのはタイトな開発スケジュールのせいで見直すべきだと提案している。
参考:Why Do US Hypersonic Missile Tests Keep Failing? They’re Going Too Fast
もし4回目の試射も失敗に終わればデジタルエンジニアリングを採用した開発体制にも疑問の声が上がるかもしれない
米空軍はブースト・グライド・ビークル(極超音速滑空体/HGV)を搭載した「AGM-183A ARRW」の試射を成功させて2021年中に量産を開始、2022年中に初期作戦能力の獲得を宣言すると議会の公聴会で豪語していたが2021年4月、7月、12月に行われた試射ではB-52Hからの切り離しやAGM-183Aのブースター点火に失敗して肝心の飛行データ収集に失敗している。

出典:Air Force photo by Matt Williams
このような状況についてジョン・ハイテン統合参謀本部副議長(現在は退任)は「極超音速兵器の開発競争で中国に米国が負けるのは未成熟な技術を開発する過程のテストにおいて失敗を許さない官僚主義や議会が問題で、萎縮した米軍は極超音速兵器のテストを過去5年間で9回しか実施していないが同じ期間に中国は数百回のテストを行っている」と語り注目を集めていたが、米メディアのDefense Oneも米政府説明責任局も「実用化を急ぎすぎているためだ」と主張して現実的な開発スケジュールに見直すことを提案しているのが興味深い。
Defense Oneは弾道弾迎撃システム「THAAD」が開発中に6回連続で模擬ターゲット迎撃テストに失敗して設立された委員会が「THAADの失敗は複雑な技術開発を短期間で達成すると設定された自滅的スケジュールに原因があり、設計・製造・管理の全てに不備が存在して開発状況を監視する政府の体制にも問題があるため開発スケジュールを現実的なものに見直すべきだ」と提言したことを引き合いに出し、緩やかな開発スケジュールに移行したTHAADは再開された13回の模擬ターゲット迎撃テストで1度も失敗がなく「委員会の提言は正しかった=初歩的な要因で試射に3回連続で失敗しているAGM-183Aも同じだ」と指摘している。

出典:ロッキード・マーティン AGM-183A ARRW
米政府説明責任局(GAO)も2021年4月に発表した報告書の中で「極超音速ミサイル開発が直面している多くの問題は国防総省が従来の兵器開発プロセスをバイパスする新しい開発権限を行使しているためで、未熟な技術と6ヶ月以内にプロトタイプ製造して5年以内に量産ミサイルを配備するという積極的なスケジュールにある」と指摘、つまりGAOは「国防総省は兵器の従来プロセスを無視して開発期間を短縮するため未成熟なデジタルエンジニアリング採用を強行、全く新しいプロセスの下でAGM-183Aを開発しようとしているため問題が起きている」と言いたいのだろう。
Defense OneやGAOの指摘が正しいのかは何とも言えないが、少なくとも国防総省や空軍が極超音速兵器の開発で中国に負けている状況を早く解消したいと焦っており、一刻も早く極超音速兵器を実用化することに執着しているのは事実だ。

出典:Air Force photo by Giancarlo Casem B-52Hに搭載されるAGM-183A ARRW
因みにデジタルエンジニアリング採用を主導した米空軍のウィル・ローパー次官補(現在は退官)は「従来プロセスでAGM-183Aを開発すると初期作戦能力の獲得は2027年になるが、デジタルエンジニアリングを採用して開発したAGM-183Aは僅か4年で実戦配備できる」と語っていたことがあり、もし4回目の試射も失敗に終わればAGM-183Aの開発自体だけでなくデジタルエンジニアリングを採用した開発体制にも疑問の声が上がるかもしれない。
関連記事:米空軍が極超音速兵器AGM-183Aの試射に3回連続で失敗、2021年中の量産開始は不可能に
関連記事:米軍ナンバー2の警告、極超音速兵器のテストを過去5年間で米国は9回VS中国は数百回
※アイキャッチ画像の出典:ロッキード・マーティン AGM-183A ARRW






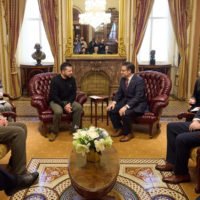














中国は第2世代の極音速ミサイル作ってるのにこれはきついね
デジタルエンジニアリングとか新しい開発手法に導入するのはもっと当たり障りのない兵器にしたほうがいいと思う
戦略を大きく変える兵器は古典的な方法で手堅くいかないとまた空母みたいに失敗してコストと時間を無駄に浪費するだけだと思うな〜
やり方の違いだけで、中国だって裏では無数に失敗はしていると思う
アメリカは予算の使い方にきちんと監視の目があるから失敗は失敗として表に出るけど
中国の場合は馬鹿正直にいちいち公表しないだけだろう
極超音速兵器だけじゃないけど、中華イージスだって空母だって原潜だって第五世代機
だって、中国方式は金と人と設備を費用対効果なんてお構い成しに湯水の如く使って
作り上げるやり方に見える、一種の人海戦術とも思える
とにかく作っては試験して何度失敗しようが悪かった点を見直しては、どんどん作って
試験しての繰り返しで最後にはものにする
専制国家で予算の監視が甘いから出来る技だけど、結果を出すって点では確実なやり方にも思う
それを支える人材と工業力があることもうまく行ってる(ように見える)一因と思われます。
資金と工業力に欠けているコンペティターはとかく質的優位を主張して大型兵器や自称ゲームチェンジャーに走りがちですが、ここ数年のアメリカはその傾向があるように見られます。
地道な基盤整備以外、冷戦を勝ち抜く方法はないんですけどね。
全く記事を読んでいないんですか?
失敗そのものを問題にしているんじゃ無いんですよ。
デジタルエンジリアニングが失敗だったら第6世代戦闘機開発計画も既に躓いてる事になるが大丈夫なのか
デジタルエンジニアリングは検討作業をシミュレーション解析で実験等に代用し、作業のデジタル化で設計プロセス(基本設計→詳細設計→製造設計)を大幅に効率化できるという利点があります。
所詮は開発ツールなんで適用するには一定の範囲と前提があります。使う側がそれを見誤らず使いこなせば、開発の期間とコストをそれなりに圧縮可能で非常に有効な開発手法です。
デジタルエンジニアリング自体も今後更に発展熟成されていくことになるかと。
同じくデジタルエンジニアリングを採用しているNGADプロトタイプやB-21は今のところ順調に開発が推移中と発表されてるので手法自体は間違ってない筈ですが…
既存技術の組合せであればもんだいないかもしれないが、技術的な挑戦を必要とするものには向いていないのだろう。
閃きや新しい発想が必要だからしょうがない
過去に実績の無い新規技術においては、実験や実績による検証データの裏付がないとデジタル解析結果の信頼性を確保できません。向いてないというより、信頼できないことを理解の上で運用しないといけない。
その場合でも、例えば風洞試験の回数を減じる等の効果はあります。それだけでも期間とコストを削減できるわけで有効な開発手法です。
結果が出るまで予算と人員ぶっ込めば良いんだよ、とまぁ冗談はおいといて腐っても超大国たるアメリカでさえこの開発状況って事は我が国の極超音速兵器はいったいどうなるんだよ
ひょっとして川崎重工に頼もうとしてた射程2000kmの対艦ミサイルを取り消したのって開発リソースを集中させるため?
青天井の予算をつけて潤沢な人材を投入して…というのは20世紀まではアメリカの十八番だったんですけどね…まさか米国防総省の開発案件で「予算削減のために工期圧縮しすぎて開発が座礁」という話を聞くことになるとは思いませんでした。
記事中で触れられている通り、従来から非常に厳しかった議会の予算監視に加えてここ何年かのホワイトハウスからの軍事費削減圧力、そして国防総省の上層部による早期実用化圧力が重なって現場がねじ切れてしまったという感じなんですかね。
ところで27年というと日本の島嶼防衛用高速滑空弾の早期装備型の配備が予定されている頃ですね。初期のロードマップだと25年に早期装備型の開発を終了してから性能向上型の研究開発に入るとあります。このあたりで米国の滑空弾の技術成果を日本が見込んでたりするのかどうかは自分には分からないですが(例えば実験設備の利用状況が重複するというようなことはありうる)、米国の開発遅延があまり酷いようだと日本の滑空弾プログラムへ影響を及ぼすことになったりするんですかね。
急がば回れは洋の東西関係なく真理なんやな。
ここ何年どころか冷戦後は議会が余計なことやロビーばっかりするせいで成功例自体少なすぎませんかねデジタルエンジニアリング導入以前から。フリーダムとかコマンチぐらいで外野掃除しておくべきでしたよ