イタリア陸軍は老朽化したダルドの交換に150億ユーロ(取得コストは52.3億ユーロ)を投資する予定で、開発を主導するレオナルドのパートナーにKNDSとラインメタルが名乗りを上げており、イタリア陸軍は新規開発を希望しているらしい。
参考:Italy tees up $5 billion-plus program to build 1,000 combat vehicles
プログラムとして成立すれば中々面白いものになるはずだ
ロシアのウクライナ侵攻を受けて「伝統的な地上戦力」に対する再評価に注目が集まり、イタリアでも現実的な脅威の登場を受けて「陸上戦力の更新」が本格化、ラウティ国防次官は「アリエテは200輌中50輌しか運用状態にない」「NATOの義務を果たすには250輌以上の戦車が必要」「2024年から戦車取得のための予算計上が始まる」と、計画に詳しい関係者も「レオパルト2A8が133輌必要」と明かしていたが、メローニ政権もレオパルト2A8の取得費用を盛り込んだ予算を提出した。

出典:Corporal-chef Sedeyn Ritchie, Belgian combat camera team
レオナルドとKNDS(合併した独KMWと仏Nexterの持株会社)も戦略的提携に署名したと昨年12月に発表、この協定は「イタリアが希望している欧州戦車計画(Main Ground Combat Systemのこと)への参加」「発注が確実視されているレオパルト2A8のワークシェア」に関するものだと報じられており、イタリア陸軍の主力戦車は「アップグレードされたアリエテ」と「新規調達するレオパルト2A8」で構成され、これを将来的にMGCSで更新するつもりなのだろう。
さらに興味深いのは両社の提携範囲が「Army Armored Combat System=A2CS」にも及ぶと噂されている点で、A2CSは以前「Armored Infantry Combat System=AICS」と呼ばれていたダルドの後継プログラムのことだ。

出典:public domain
メローニ政権は予算案の中で「ダルドの後継プログラムに4,890万ユーロを支出予定」「最終的なプログラムコストは150億ユーロに達する」「これは伊産業界、雇用、ノウハウを最大限活用するものでなければならない」と指摘していたが、イタリア軍高官は「A2CSプログラムを開始するため数ヶ月以内に産業界のパートナーを決定する」「コスト的にも技術的にも複雑なプログラムを単独開発できる国があるとは思えない」「そのため多国間の協力が期待されレオナルドとKNDSの提携はその第一歩だと確信している」と言及。
KNDSも「イタリアの装甲車輌開発は両社が協力できるプログラムかもしれない」と述べ、米ディフェンス・メディアは「KNDSがボクサーベースの設計(2022年に披露したIFVバージョン)をイタリアに提供するかもしれない」と報じているが、この高官は「国内投資や雇用の問題だけでなくシステムのロジスティクスやアップグレードを考慮すると伊産業界による設計が望ましい」と主張しているため、設計は既存車輌をベースにしたものではなく「ロジスティクスやアップグレードがコントロール可能なイタリア主導でなければならない」という意味だろう。

出典:Lukas1325 / CC BY-SA 4.0 Lynx KF-41
既にLynx KF-41を提案しているラインメタルは「イタリアに技術移転と設計権限を与えることが出来る」「もし0から車輌を設計すれば5年から7年ほどの時間が必要でプログラムの遅れに繋がる」「現時点でKNDSは提供可能なIFVを持っていない」と語り、戦略的提携を結んだKNDSに対して立場や交渉力で劣っていないと主張している。
因みにダルドの後継プラットフォームは「最大1,000輌もの調達に発展するかもしれない」と報じられているため、KNDSもラインメタルも開発パートナーに選ばれることを望んでおり、レオナルドも150億ユーロ(取得コストは52.3億ユーロ)のプロジェクトに備えてIvecoの車輌製造部門(Iveco Defence Vehicles)の買収を検討しているらしい。
イタリア陸軍がA2CSに要求している能力にはUAVやUGVとの協調能力が含まれているので、プログラムとして成立すれば中々面白いものになるはずだ。
関連記事:イタリア、2024年度からレオパルト2、次期IFV、HIMARSの調達を希望
関連記事:イタリア、レオパルト2A8の新規調達とアリエテのアップグレードを実施
関連記事:イタリアで当面のギャップを埋める戦車調達が浮上、レオパルト2A7導入?
関連記事:イタリア陸軍、アップグレードされた主力戦車アリエテのプロトタイプが完成
関連記事:ポーランド陸軍の次期主力戦車に新たな挑戦者、イタリアが国際共同開発を提案
※アイキャッチ画像の出典:Krauss-Maffei Wegmann GmbH&Co.KG RCT120を取り付けたバージョン
















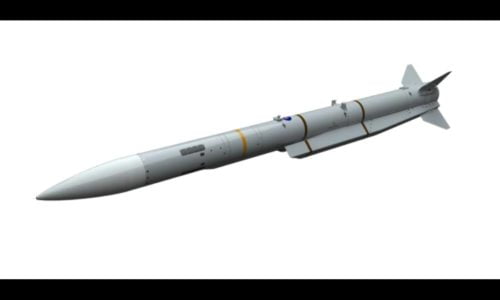




>イタリア陸軍がA2CSに要求している能力にはUAVやUGVとの協調能力が含まれている
UAVなどとの連携能力が求められるのは時代だけど、UAVなどの規格を統一する機運はあるんだろうか
一国だけの運用ならともかく多国間での共同作戦や有事での装備品供与などを考えると、通信規格などをある程度共通化しとかないと困りそうだけど
MGCSはイタリアはともかくドイツ/フランスって時点で嫌な予感しかしないけど上手く行くんだろうか
ダルドの後継が最大1000両とは羨ましい
そっくりさんの89式IFVの後継はどうなっているんでしょう
共通戦術装輪車(IFV)は150両ほどの予定らしいですし、思ったほど多くない…
装輪でこの数ですと、装軌の車両はさらに少ないのでしょうか
歩兵戦闘車の件に関してはパトリアの歩兵戦闘車に積んでる機関砲を試験のために輸入
するみたいだから
もしかすると即応連隊は三菱、普通科連隊はパトリアの歩兵戦闘車を配備するかもしれないらしい
プーチンというかロシアへの抑止力として北海道には装軌式の車両を第七師団用に配置してほしい物です。
調達数が少ないでしょうから89式の調達失敗を教訓に無理な国産化を止めてスペアパーツを大量につけて輸入で済ませましょう。
清原…
敵陣営のドローンや地雷への対処能力はどの程度になるんでしょうねぇ
ウクライナで色々と戦訓あったでしょうし気になるところ
戦闘機と同じように日英伊で共同開発してくれ!
何処かの89式と違って国際共同開発なら生産量増やせるし
戦車と違って国毎に譲れない条件みたいなのもそんなに無いでしょ
揉めそうなのは乗員数位か?
そんなに少ない?本体サイズ、重量、履帯の種類(素材や形状)、パワーパック、乗員配置、拡張性のある設計(配線等の装備追加のしやすさ)、装甲材の質とか色々と揉めそうだけど?やれ結晶粒微細化鋼板とかユーロパワーパックじゃなく10式のデチューンしたパワーパック使いたいとかありそうだ。
ダルドは見た目が無茶苦茶好みなので欲を言えば近年流行りの不格好な形状ではなく、独自の形状になって欲しいものです…
今現在、ウクライナで評判の良いIFVは。
米国のブラッドレーとドイツのマルダーでしょうか。
旧ソ連製の評判は全滅のようですね。
やっぱり、重い物の方がが良いような気がします。
イタリアがどのような戦訓を引き出しているのか知りたいものです。
そもそも一口にIFVといってもそれぞれ設計思想がまるで違いますが、ブラッドレーは操作が煩雑、機動性は劣悪、火力は貧弱、整備性は極悪、調達コストは最悪、と優れた評価はされていませんよ
例えばスロヴィキンラインでは多数のBMPが連携して大量のコンクールスを投射して攻勢開始直後にウクライナ軍機甲部隊を粉砕してしまいましたが、こんなことはブラッドレーでは出来ません
エアバースト射撃なんてアメリカの無駄な豪華主義の極地ですね、あんなことするくらいなら短砲身砲でもつけて曲射した方がはるかに安全かつ低コストで大きな効果を実現出来ます
米国製は元々、要求が多いので、複雑にはなりますね。
”例えばスロヴィキンラインでは多数のBMPが連携して大量の
コンクールスを投射して攻勢開始直後にウクライナ軍機甲部隊を粉砕”
そういう、シーンもあると思います。それこそ設計思想にもよるのでは。
”重い物の方がが良いような気が”と書いたのでわかると思いますが。
素人は、任務達成の上で、生存できることを重要視します。
イタリア軍がどう考えるかは、また別のことですが。
確かに単体での生存性、特に搭乗員の生存率は比べ物にならないでしょう。
しかしながら運用という点では数が用意できなければそもそも機械化率が下がってしまったり、火力支援のできない装甲車などが増えるということになります。装備の種類が違えば同じ役割をこなすことは難しく、戦力の集中運用が難しくなったり、撃破された場合の補充が続かなかったりといった問題も生じますね。
現にウクライナでは攻勢時にM2を含む多くの重装甲車両が撃破され、進軍速度を大きく落としました。修理されたり追加の供与を受け取ったりなどで稼働数自体は回復したものの、必要な時に必要な部隊に届くわけではなく結局攻勢は失敗に終わりましたね。(もちろんそれだけが理由ではないですが)
BMP/BMDの特筆すべき点は歩兵旅団のほとんどを機械化できるだけの数を用意できたことです。既に相当数が撃破されていますが、それだけの数を投入しているということ自体が脅威であり運用思想の優れる点でもあります。
もちろんおっしゃるとおりイタリア軍がどのような運用思想を持っているかというのが最終的な決定に繋がるのも事実ですが、それはここで話していても分からないことですので…。
長文失礼いたしました。
最大1,000両とか言ってるからロシア・ウクライナ戦争の戦訓は相当汲んでそうな雰囲気
理想的には全NATO加盟国で共通化して大量導入するのがベストだけど各国とも自国の利権は手放したくなくて、そうはならないのがお約束
”数は正義”というのは、
この戦役での教訓の一つとは思いますが。
双方がそれなりの数量を持つと仮定すれば、
結果は質の優位を持つ側に優位と甥もいます。
質のみならず、量も必要ということかと。
イタリア陸軍が本当に1,000両を揃えるなら、
それは、質を備えた量を整備すると考えて良いのでは。
マルダーの再生産かブラッドレーではいけないのか?
製造から被弾廃棄までの稼働寿命を考えれば既に実績のあるマルダーの再大量生産かブラッドレーのライセンス生産で旧新車双方に利用できる整備補修基盤を強化した方が良いのではと考えてしまう。
過去の遺産を利用しつつイスラエルのように独自改修を認めさせた方が得策と思う。
車種が変わるごとに工具や治具、度量衡の相違、作業手順や細かい作業標準に書かれないノウハウが多岐に渡ると高い稼働率と即応性が維持できない。
新規開発はオタ的には魅力だが、兵站物流保守管理からすると仕事を減らす努力を望むところ、新規生産して予算超過で配備数削減の未来が見える。
それを開発した国が次世代に移っているか移ろうとしているのに設計思想が古い旧式をわざわざ生産する意味とは。どちらも新規製造なんてしてますか?どんな形であれ生産した実績があるから問題無いと言うのは流石に製造業を舐めすぎでは?
ラインが閉じられているなら金型なり治工具の類は廃棄済みでしょう。実績あるものと言ってもその為に再度作り直すなら新規製造とそこまで変わるかと思いますけどね。
独自改修にしてもどの部分をどのくらいするかでテストの度合いも違うし、例に出した外国製陸戦兵器のイスラエルの改修は製造済みの車両がメインで新規製造なら自国の要望を反映した物しかないと思います。
イスラエルが既存のものを生かしつつ極めて高いレベルの改修モデルを作れていますか?どうしても見た目に無理矢理な設計の車両があるでしょうし、無理な改造をすれば走行性能にすら悪影響を及ぼします。既存モデルが問題無いならエイブラムスとかレオ2の改修モデルを将来に渡って作り続ければ1番良い事になりますが、それをしないのは何故なんですかね。
2000年代以前設計のIFVは対IED耐爆化がそもそも無茶。GVW設定が低いので付加機材の積載限度が低い。総合性能で30t台が限度。エンジンルームが拡張性皆無で高出力化は容易になくHV化など大改造せにゃ到底無理。砲塔、車体共にAPS防護の最適配置化が無理。より大口径砲を二人乗り砲塔で搭載は容易にない。そもそも戦闘思想が古すぎて今後標準化されるSA化にも適当じゃない。
某国の換装車体とかあんなんはAMPVに同じくAPCならいざしらずIFVで等は非常識すぎる。だったら車幅3mのハイエンド装輪装甲でのIFVと性能差なんて無いに等しい。量産効果を加味すれば尚更に存在価値の合理的説明など遠のくだろう。機動運用性も性能の内といい始めれば尚更の事。
KNDS案の履帯型ボクサーはAMPVに近くバリエ数を優先のAPCメインの選択肢だろう。1000両と言う事はその内のIFVは多くて2割でAPCが大半だな。IFVの性能を優先するか、その他の多くでの運用効率を優先するか、一車種で全部賄うにはどっちか選ばにゃならん。イタさんのIFV計画はそれを決した段階でもない。